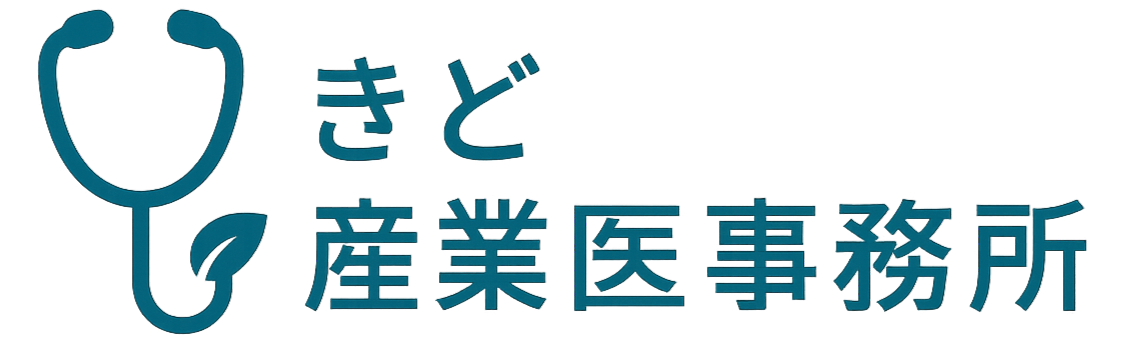ストレスチェック、やるだけで終わっていませんか?
「うちは毎年ちゃんとストレスチェックやってますよ。」
企業のご担当者様から、そんな声をよく聞きます。
でも、ストレスチェックの目的は、単に実施することではありません。
本当に大切なのは、「チェックのあとに何をするか」です。
1. ストレスチェックの本来の目的
ストレスチェックは、従業員が自分のストレス状態に気づき、必要に応じて対処するための制度です。
また、企業にとっては「職場環境の改善のきっかけ」にもなります。
つまり、目的は「組織としてのリスク管理」であり、「個人の早期対応」です。
やるだけで終わってしまうと、この目的は果たせません。
2. よくある“もったいない”運用例
例えば以下のようなケースは、実は非常に多く見られます。
- 結果を回収するだけで、フィードバックがない
- 高ストレス者に面談の案内をしていない
- 組織分析をしても、その後の改善策が検討されない
こうした状態では、「ストレスチェックが形だけのもの」になってしまいます。
3. 面談は“問題発見”の貴重なチャンス
高ストレス者への面談は、問題の“早期発見”と“対応の糸口”になります。
たとえば、勤務時間では見えない悩みや、組織内の人間関係の課題などが見えてくることも。
産業医の面談を通じて、本人への支援だけでなく、職場環境の改善提案にもつなげることができます。
4. 組織分析は“気づき”のヒント
部署ごとのストレス状況を見える化する「集団分析」は、今の職場が抱えるリスクを客観的に示す手段です。
分析結果を、衛生委員会などで共有し、具体的な改善策を話し合うことが、ストレスチェックを「活かす」運用につながります。
まとめ
ストレスチェックは「やること」ではなく、「活かすこと」が大切です。
チェック後の面談や職場分析をしっかりと活用することで、従業員の健康を守り、職場の安心感も高まります。
「ストレスチェック後の対応を見直したい」「高ストレス者面談を依頼したい」など、
お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 産業医コラム2025年5月19日“沈黙の不調”を見逃さない — テレワーク時代のメンタルヘルス対応
産業医コラム2025年5月19日“沈黙の不調”を見逃さない — テレワーク時代のメンタルヘルス対応 産業医コラム2025年5月18日産業医契約、訪問回数より大切なこと
産業医コラム2025年5月18日産業医契約、訪問回数より大切なこと 産業医コラム2025年5月18日ストレスチェック、やるだけで終わっていませんか?
産業医コラム2025年5月18日ストレスチェック、やるだけで終わっていませんか? お知らせ2025年5月13日ホームページをリニューアルしました。
お知らせ2025年5月13日ホームページをリニューアルしました。