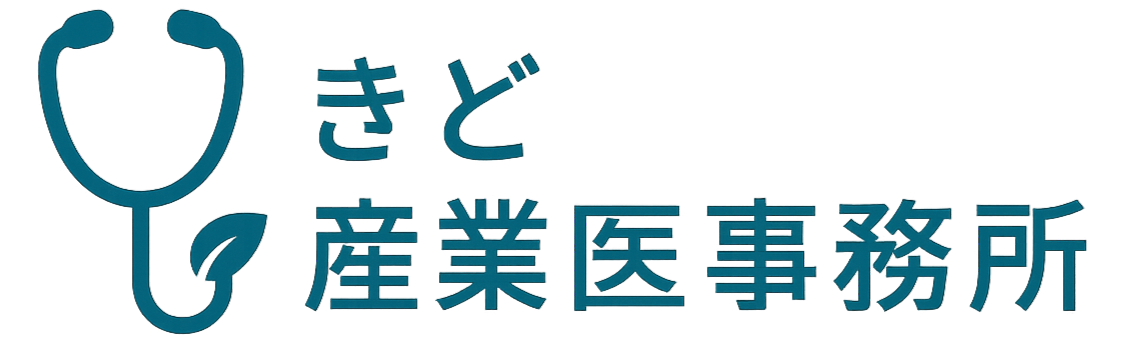“沈黙の不調”を見逃さない — テレワーク時代のメンタルヘルス対応
1. はじめに ―― なぜ「見えにくさ」が問題なのか
テレワークは、柔軟な働き方を実現しつつ通勤ストレスも削減できるなど、多くのメリットがあります。一方で、産業医の立場からは「働く人の状態が把握しにくい」という新たな課題が浮かび上がっています。
出社していれば、同僚の表情や声色、ちょっとした雑談から “いつもと違う” サインを感じ取りやすいものです。しかし在宅勤務では、こうした非言語情報がオンライン会議やチャットの向こう側に隠れてしまいます。
「朝のログインはしているが反応が遅い」「オンライン会議でカメラをオフにすることが増えた」―― これらは本人も気づかないうちに蓄積する“沈黙の不調”の一端かもしれません。本稿では、テレワーク環境で見えにくくなったメンタル不調を早期に発見し、組織としてケアするための実践的なポイントを解説します。
2. テレワーク特有の“沈黙のサイン”を知る
テレワークの長期化によって、従来とは異なるメンタル不調のサインが報告されています。代表的なものを整理すると下表のとおりです。
| サイン | 従来勤務での把握方法 | テレワークでの変化 |
|---|---|---|
| 表情・声のトーン | 直接対面で察知 | オンライン会議でカメラOFFだと確認できない |
| 業務パフォーマンス | 上司が隣席で把握 | 成果物ベースの評価となり、変化が遅れて見える |
| 遅刻・欠勤 | タイムカードで可視化 | ログオン・ログオフ時刻が曖昧になりやすい |
⚠ ポイント
- “顔が見えない”ことで上司や同僚が異変を捕捉しづらい
- 連絡がチャット中心になると、短文やスタンプだけでは感情を読み取りにくい
- 生活リズムが乱れても通勤がないため発見が遅れる
こうしたサインは、早期に拾い上げれば軽症のうちにフォローできますが、蓄積すると長期休職や退職につながる恐れがあります。
3. 企業が講じるべき三つの対策
3-1. 「映像あり」1on1で非言語情報を可視化
月に1回程度、必ずカメラONで1on1を行うルールを設けましょう。ポイントは「面談のための面談」にしないこと。業務報告の前後に、雑談や最近の悩みを自然に聞く時間を設けることで、オンラインでも対面に近い情報量を確保できます。
実践ヒント
- いきなり深刻な話をせず、アイスブレイクを用意
- 服装や背景に目を配り、生活リズムの乱れがないかをさりげなく確認
3-2. オンラインストレスチェック+即日フィードバック
年1回のストレスチェック義務はテレワークでも変わりません。
- Webフォーム型にすることで在宅環境でも回答率を保ちやすい
- 結果を即日フィードバックしてセルフケア教材と併せて提示すると、自覚と行動変容が促進
高ストレス者には、産業医面談をオンラインでも案内し、過度な残業や孤立感などの背景要因を早期に把握します。
3-3. バーチャル職場巡視で環境要因をチェック
物理的な巡視が難しい場合は、アンケートや写真共有でデスク環境を確認する「リモート巡視」を導入します。
- 室温・照度、姿勢、椅子の高さなどをチェックリスト化
- Webカメラを通じて実際の作業姿勢を示してもらうと、腰痛・眼精疲労の予防指導が具体的になる
4. 産業医が果たす四つの役割
| 役割 | 具体的な支援内容 |
|---|---|
| ① 一次面談窓口 | 高ストレス者や上司が心配する従業員をオンライン面談し、医療機関受診や就業配慮の助言を実施 |
| ② 管理職コーチング | “カメラOFF文化”の改善方法、チャットの声がけ例などを研修で提供 |
| ③ データドリブン分析 | ストレスチェック×勤怠データで過重労働部門を抽出し、具体策を提案 |
| ④ 就業措置の調整 | 在宅継続・時短・段階的復職などを、本人・上司・人事の三者面談で合意形成 |
産業医が伴走すると、医学的知見と職場実情の“翻訳者”として両者をつなぐ役割を果たせます。
5. ケーススタディ — IT企業A社(従業員100名・在宅比率80%)
背景
Slackでのやり取りが業務連絡中心となり、雑談チャネルが形骸化。孤立感や業務過多が原因で1年に5名がメンタル休職。
介入プロセス
- 産業医が全チームに月1回オンライン面談を導入
- ストレスチェック結果を衛生委員会で共有し、ペアプログラミング復活&雑談タイム10分を朝会に追加
- 管理職へ「チャットで気づく早期声がけ」研修を実施
結果(6か月後)
- 高ストレス者率:25% → 15%
- メンタル休職:5名 → 1名
- エンゲージメントスコア上昇(社内アンケート)
キーポイント:面談・データ・研修をセットで行うことで「気づける・声かけられる・行動できる」のサイクルが回り始めた。
6. まとめ 〜 沈黙を破るのは“対話”と“データ”
テレワークは生産性と柔軟性を高める一方、不調が可視化されにくいリスクも抱えています。
- 映像あり対話で人と人をつなぎ直す
- ストレスチェック×勤怠データでリスクを数値化
- 産業医の伴走で施策を職場に根付かせる
これらの取り組みは、従業員の安心感と組織の持続的成長を同時に支える土台となります。
📩 まずはお気軽にご相談ください
「オンライン面談の進め方が分からない」「高ストレス者対応が後手に回っている」など、お悩みがあれば[お問い合わせフォーム]からご連絡ください。初回相談は無料です。
働く人の笑顔こそ、企業の力になる。
きど産業医事務所は、テレワーク下でも従業員の健康と安心を守る仕組みづくりをサポートします。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 産業医コラム2025年5月19日“沈黙の不調”を見逃さない — テレワーク時代のメンタルヘルス対応
産業医コラム2025年5月19日“沈黙の不調”を見逃さない — テレワーク時代のメンタルヘルス対応 産業医コラム2025年5月18日産業医契約、訪問回数より大切なこと
産業医コラム2025年5月18日産業医契約、訪問回数より大切なこと 産業医コラム2025年5月18日ストレスチェック、やるだけで終わっていませんか?
産業医コラム2025年5月18日ストレスチェック、やるだけで終わっていませんか? お知らせ2025年5月13日ホームページをリニューアルしました。
お知らせ2025年5月13日ホームページをリニューアルしました。